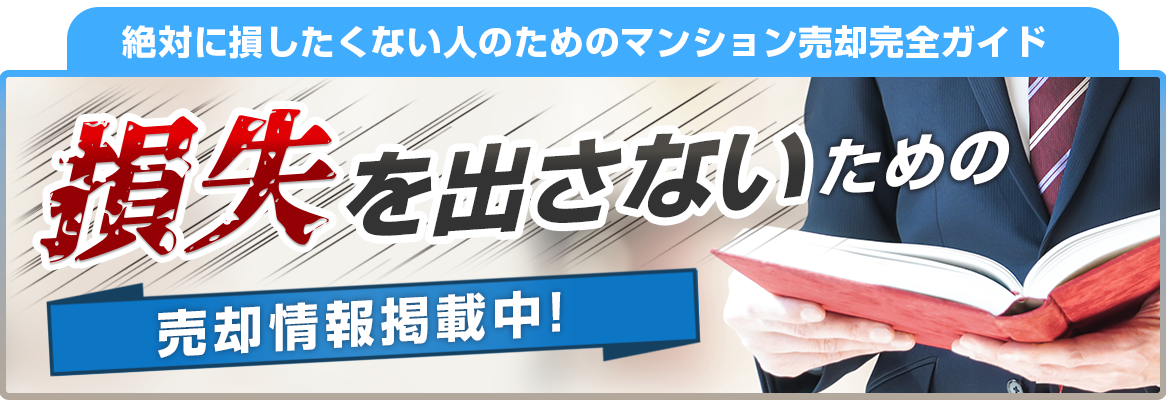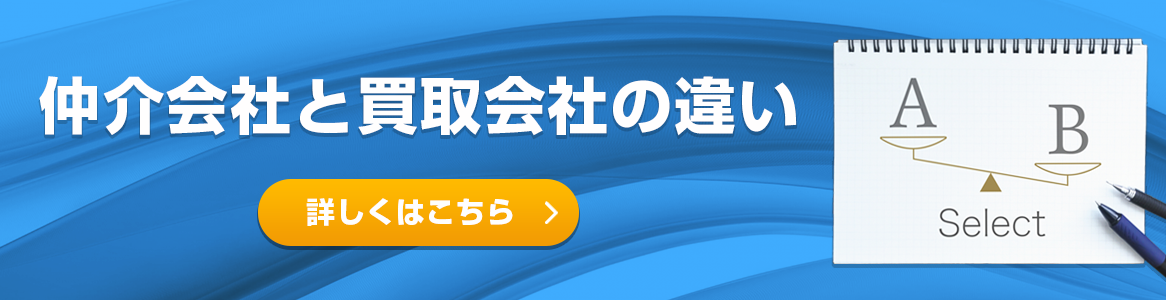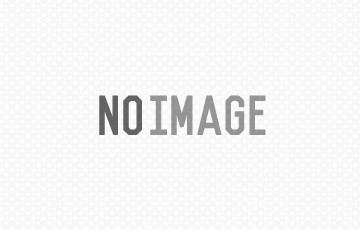ワンルームマンション投資の損切りガイド

ワンルームマンション投資で思うような収益が出ず、毎月のローン返済や空室リスクに悩んでいませんか?
「このまま持ち続けて大丈夫なのか、それとも損切りして売却すべきか…」と決断に迷う方も多いでしょう。
実は、不動産投資における損切り(含み損を抱えた資産を売却して損失を確定すること)は、決して珍しいことでなく、資産を守るための重要な戦略です。
本記事では、損切りとは何かとなぜ必要かを解説し、損切り判断の基準やベストなタイミング、そして損失を最小限に抑える売却方法について詳しく紹介します。
ワンルームマンション投資における損切りはなぜ必要なのか
「損切り」とは、投資した資産が当初の見込みよりも価値や収益が下がってしまった場合に、それ以上損失を拡大させないよう手放すことを指します。
株式投資などでも使われる言葉ですが、不動産投資においても同様です。
ワンルームマンション投資で毎月赤字が続いているような場合、どこかで見切りをつけて物件を売却し、損失を確定させる決断が必要になることがあります。
損切りが必要とされる最大の理由は、これ以上の損失拡大を防ぐためです。
うまくいかない投資物件を抱え続ければ、時間の経過とともにさらに資産価値が下落したり、損失額が増えたりするリスクがあります。早めに損切りすることで、傷が浅いうちに撤退し、損失を最小限に抑えることができます。
たとえば、ある物件で月々数千円程度の赤字が出ているなら、将来の収支改善も考えつつ様子を見る余地があります。
しかし、毎月何万円もの持ち出しが続くようであれば、その赤字分は所得税の節税効果を差し引いても確実に現金が減っている状態であり、早期に損切りを検討すべきサインです。
また、損切りをせず赤字物件を抱え続けることには別のリスクも伴います。
毎月の赤字補填が家計を圧迫すれば、生活にも支障をきたしかねません。それだけでなく、ローン返済が滞るような事態に陥れば、個人の信用情報にも傷がつき、他のローン(マイホーム購入や車のローン、クレジットカードなど)が組めなくなったり、最悪の場合自己破産に至る可能性すらあります。
実際、不動産投資で大きな失敗をした人の中には、この判断が遅れたために深刻な状況に追い込まれたケースもあります。 損切りは決して「負け」や「失敗」ではありません。それ以上の大きな損失から自分を守る自己防衛策であり、資産を健全に保つための前向きな戦略です。
むしろ、上手な投資家ほど損切りの判断が早く、余力をもって新たな投資機会に資金を振り向けています。
次章では、具体的にどんな状況になったら損切りを検討すべきか、不動産投資の損切り判断の基準について見ていきましょう。
ワンルームマンション投資における損切りの判断基準:売却を検討すべきケース
不動産投資において損切りを判断する目安として、一般的に次のような状況が挙げられます。
これらに当てはまる場合は、ワンルームマンションを売却(損切り)すべきタイミングかどうか、前向きに検討しましょう。
キャッシュフローが慢性的に赤字
家賃収入からローン返済や管理費・税金など経費を差し引いた収支が長期間マイナスの場合です。退去直後や一時的な修繕費発生で一時的に赤字になることはあっても、毎月のように持ち出しが続く状態は損切りのタイミングかもしれません。
特に、その赤字額を埋める収入源が他になかったり、貯蓄を切り崩す状況が続いているなら危険信号です。
毎月数千円程度の赤字で生活に支障がないレベルなら様子見もできますが、毎月何万円もの赤字となれば早めに損切りを検討した方が良いでしょう。
今後家賃の大幅アップなど劇的な改善見込みがない限り、塵も積もれば山となる赤字は放置できません。
物件の資産価値が大きく低下している
購入時よりも物件の市場価値が明らかに下がっており、この先も大きな回復が見込めないケースです。
新築で購入した投資マンションが年数の経過とともに中古市場での評価額を下げていくのは自然なことですが、立地の需要低下や競合物件の増加などで想定以上の価格下落が起きている場合は注意が必要です。
購入価格と現在の売却予想価格を比べて大きなギャップ(含み損)が生じているなら、持ち続けるほど損失が拡大する可能性があります。将来的にエリアの再開発などプラス要因がない限り、早めに売却して現金化した方が得策といえます。
特に地方物件で人口減少が著しい地域にある場合や、購入時に相場より割高で掴んでしまった場合は、時間経過とともに回復どころかさらに目減りするケースが多い点に注意しましょう。
将来の修繕費や金利上昇などコスト増リスクが高い
築年数が経ち、大規模修繕や設備交換など多額の費用発生が避けられない見込みの場合も検討が必要です。
ワンルームマンションでは築15〜20年を超えたあたりから修繕積立金の値上げや、エレベーター・給排水設備の更新などコスト増要因が増えてきます。
例えば新築当初2,000円だった管理費・修繕積立金が、15年後には月6,000円に上がる例も珍しくありません。
こうした経年による維持費アップはキャッシュフローを徐々に悪化させ、利回りを押し下げます。また、変動金利でローンを組んでいる場合は将来的な金利上昇リスクにも備えなければなりませ。
現在は低金利でも、金利が1〜2%上がれば月々の返済額が大幅に増え、ギリギリだった収支が一気に赤字転落する恐れがあります。
こうした将来のコスト増要因が現実味を帯びてきたら、本格的に損切りを含めた出口戦略を考えるタイミングと言えます。
利回りが極端に低く投資効率が悪い
購入後に計算してみたら、期待していた利回りに遠く及ばないことが判明した場合です。例えば都心ワンルームの平均利回りが現在5〜6%前後と言われる中、諸経費込みの実質利回りが2〜3%しかない、あるいはマイナス利回り(元本割れ)の状態であれば、その物件を長期保有するメリットは薄いかもしれません。
新築で高値掴みしてしまった物件ほど表面利回りも低くなりがちですが、購入後に後悔しても利回りそのものを変えることはできません。
資金効率の面で見ても、あまりにも低利回りな物件にお金を縛られているくらいなら、たとえ売却時に損失(元本割れ)が出たとしても、その資金を他の投資に振り向けた方が将来的にプラスになる可能性があります。
ワンルームマンション投資における損切りのベストなタイミングとは?

では、投資マンションを売却するベストなタイミングはいつなのでしょうか?
損切りの判断では、早ければ良いというものでもなく、遅すぎるのも良くありません。市場環境や税制も踏まえ、総合的にタイミングを見極めることが大切です。
できるだけ早めに決断する
基本的に、損切りすると決めたなら先延ばしせず早期に売却するのが鉄則です。
迷っているうちにも物件は古くなり、市場価格は下がり、損失額が膨らんでしまうからです。実際「売却するのであれば、古くなって価格が下がり損が大きく広がる前に手を打つことがおすすめです」と指摘されています。
不動産は築年数とともに価値が下がりやすく、特にワンルームは建物の比重が大きいため建物価値の減少=価格下落に直結します。損切りすると腹を括ったなら、市場がさらに悪化する前に行動に移しましょう。
入居者がいるうちに売却する
タイミングを計る上で見逃せないのが物件が満室か空室かという点です。
可能であれば、入居者が賃貸中の状態で売却するのが理想です。空室の物件より、家賃収入が発生している物件の方が収益物件としての魅力が高く、買主もつきやすくなります。
特に投資家向けに売る場合、「購入後すぐに家賃収入が得られる」というのは大きなアピールポイントとなり、高く売れる傾向があります。
逆に空室が続いている物件だと、買主はその空室リスクも織り込んで値下げ交渉してくる可能性が高くなります。
したがって、次の入居者が決まってから売却活動を開始する、あるいは退去予定が近いならその前に売却してしまうなど、空室期間を作らないタイミングを狙うと良いでしょう。
建物の老朽化が進む前に売却する
建物や設備の劣化が目立ってくると、買主から見た印象も悪くなり、価格交渉で不利になります。
具体的には、築年数で言えば築20年以内くらいまでに売却できるとベターです。
30年近くになってくると「そろそろ大規模修繕が必要では?」「設備の寿命が来ているのでは?」といった懸念材料が増え、買い叩かれやすくなります。
逆に言えば、老朽化によるマイナス印象が本格化する前に売却するのが、高値で売却するコツです。
特に外観や共有部の古びた感じが出てくる築15〜20年以降は、価格下落のカーブが急になる傾向があるため、「築○年以内に売る」といった目安を予め決めておくのも一つの手です。
税制上有利になる節目を考慮する
不動産売却には税金(譲渡所得税)の問題もついて回ります。物件を売って利益が出た場合、所有期間が5年以下か超かで課税率が大きく異なります。
一般的に5年超所有(長期譲渡所得)の方が税率が約20%と低く、5年以下(短期譲渡)は約39%と高税率です。
損切りの場合、多くは売却益が出ない(むしろ損失)ため譲渡所得税は発生しないと考えられますが、近年の不動産価格高騰で思いのほか高値で売却できるケースもあり得ます。
もし購入から4年〜5年未満といった時期で、売却額によっては利益が出そうな場合は、5年経過(長期譲渡)まで待つことで手元に残るお金が多くなる可能性があります。
これはレアなケースですが、売却タイミングを図る上で「5年ルール」は頭に入れておきましょう。反対に明らかに損失であれば、税金面を気にして長く持つ意味はあまりありません。
ただし居住用財産(自分や家族が住んでいる家)として一定要件を満たす場合には別途特例で損失を他の所得と損益通算・繰越控除できる制度もあります。
投資用ワンルームには通常適用されませんが、税制の特例が自分に該当しないか専門家に確認しておくと安心です。
市場環境や景気動向も見極める
不動産市況や景気の動向も、売却のタイミングを判断する重要な要素です。例えば今後金利が上昇局面に入れば、不動産価格が下落傾向になる可能性が高いと言われます。
また、人口動態や地域の需給バランスも無視できません。お持ちの物件のエリアで空室率が上昇傾向にあったり、新築マンションの供給が過剰になっているようなら、遅かれ早かれ価格にも影響が及ぶでしょう。
反対に、たまたま近隣で再開発計画が浮上しそう、大型商業施設ができる等のプラス材料が見込めるなら、それまで待ってから売る方が良いかもしれません。
このように、不動産市況の先行きにもアンテナを張り、「売るならいつがベストか」を常にシミュレーションしておくことが大切です。
損切りを決めた際の売却の流れと必要な準備
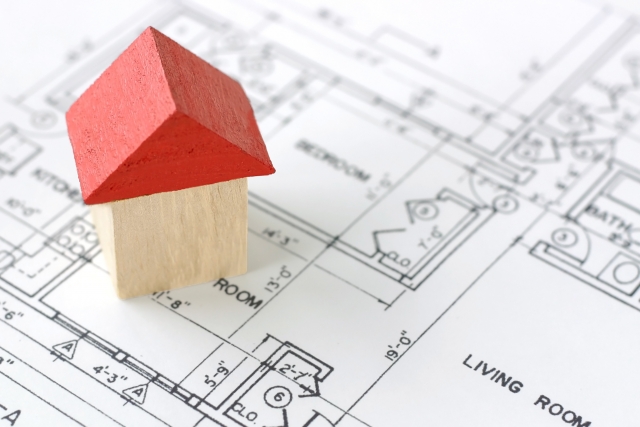
売却に向けた準備では、必要書類の収集や市場価格の調査など、入念なチェックが欠かせません。専門業者による査定を受け、計画的に進めましょう。
いざ損切りで物件を売却しようと決めたら、次は具体的な売却の手順を踏んでいくことになります。不動産売却にはいくつかのステップがあり、事前に流れを把握しておくとスムーズです。
事前準備・現状把握
まずは物件情報の整理と必要書類の準備から始めます。
具体的には、登記簿謄本(登記事項証明書)や物件の間取り図・測量図、本人確認書類、そして現在賃貸中であれば賃貸借契約書や管理委託契約書などが必要になります。
登記簿謄本には物件の権利関係や土地建物の情報が記載されており、法務局で取得可能です。
また、物件の購入時のパンフレットや資料が残っていれば用意しておくと査定時に役立ちます。併せて、現在の市場相場を調べて現状把握しておきましょう。
SUUMOやHOME’Sなどの不動産ポータルサイトで、近隣類似物件がどれくらいの価格で売りに出されているかを確認しておくと、査定結果が適正か判断しやすくなります。
不動産会社に査定を依頼
書類の準備ができたら、不動産会社に物件の売却査定を依頼します。
「不動産売却・無料査定サービス」を利用すると手軽ですが、できれば複数社に査定を依頼することをおすすめします。
不動産会社ごとに得意分野や顧客層が異なるため、提示される査定額にも差が出ることがあるからです。
査定には机上査定(簡易査定)と訪問査定があります。机上査定は簡単な物件情報から相場ベースで算出するものでスピーディですが精度はそこそこ。
訪問査定は実際に担当者が物件や部屋の状況を確認して行うため、より正確な価格がわかります。時間に余裕があれば訪問査定も依頼し、査定額だけでなく売却戦略やサービス面も含めて比較検討しましょう。
なお、「査定額が一番高い会社=ベスト」とは限りません。極端に高い査定を出す会社は売却まで時間がかかる可能性もあります。
各社の販売力(買主を見つける力)や提案内容を比較し、総合的に信頼できる仲介会社を選ぶことが重要です。
媒介契約の締結(仲介契約)
仲介を依頼する不動産会社が決まったら、その会社と媒介契約を結びます。
媒介契約とは「この不動産を売る業務をお願いします」という正式な依頼契約です。
媒介契約には大きく分けて3種類(一般媒介・専任媒介・専属専任媒介)があります。
一般媒介は複数の会社に重ねて依頼できる契約、専任媒介は1社だけに依頼する契約(ただし自分で見つけた相手との直接取引は可)、専属専任媒介は1社専任+自己発見取引も不可という契約形態です。
それぞれメリット・デメリットがありますが、一般的に不動産会社は専任契約を好みます。
一方で売主側としては一般媒介の方が間口が広がる利点があります。
しかし複数社に依頼すると各社への対応が手間になる側面もあるため、信頼できる会社が見つかった場合は専任媒介で任せるのも良いでしょう。
契約時には媒介契約書に署名・捺印し、契約形態に応じて売却活動の報告頻度などの取り決めがなされます。
売却活動の開始: 媒介契約を結んだら、いよいよ売却活動のスタートです。
不動産会社は物件情報をレインズ(不動産流通機構のデータベース)に登録し、自社サイトやポータルサイトに掲載、既存顧客への紹介など様々な手段で買主探しを行います。
投資用ワンルームの場合、買主は主に投資家や地主、不動産会社(買取業者)などになるでしょう。
売主(オーナー)は居住中の売却とは異なり、基本的には買い手が見つかるのを待つ形になります。
入居者がいる場合は内見(室内の見学)は原則できませんが、希望者が現れたら収支シミュレーションや資料提供などの対応を求められることも。
空室であれば内覧に備えて室内を清掃し、見栄えを良くしておきましょう。
売却活動期間は相場価格が適切であれば数週間〜数ヶ月で買い手が見つかることもありますが、高めに出していると半年以上長引くケースもあります。
途中で問い合わせ状況を聞きながら、必要に応じて価格見直しも検討します。
売買条件の交渉
無事に購入希望者(買主)が見つかったら、次は売買条件の細かな交渉と調整を行います。一般的に買主は提示された販売価格に対して値下げ交渉(指値)をしてくるものです。
例えば「○○万円なら購入します」といった具体的なオファーがあるので、希望額とかけ離れていなければ歩み寄れるか検討しましょう。
価格以外にも、引き渡しの時期や契約日程、付帯設備の扱い(エアコン等を残すか撤去するか)なども話し合います。
投資物件の場合、賃借人の引き継ぎについて(オーナーチェンジとしてそのまま引き継ぐのが基本)確認し、敷金の精算方法なども取り決めます。
条件交渉は不動産会社が仲介役となって進めてくれるので、要望や譲れないラインを担当者に伝え、適切に調整してもらいましょう。
お互いの条件が合意に至ったら、いよいよ契約へと進みます。
売買契約の締結
売主・買主間で条件が合えば、不動産売買契約を締結します。
通常、契約当日は売主・買主双方と仲介担当者が一堂に会し、不動産会社から重要事項説明(物件に関する説明や契約内容の確認)が行われます。
その後、契約書に署名・押印し、正式に売買契約成立です。
契約時には買主から手付金を受け取ります。手付金は売買価格の5〜10%程度が一般的で、これは契約解除のペナルティ等にも関わる重要なお金です。
また同時に、売主は仲介会社へ仲介手数料の半金ほど(残りは決済時)と契約書に貼付する印紙代を支払います。契約書取り交わした後は、違約がない限り売却がほぼ確定します。
残金決済と物件引き渡し
売買契約から1〜3ヶ月ほどの期間を目安に(買主の融資手続き期間を考慮)、物件の引き渡し・決済を行います。
決済日には、買主から残代金(売買価格から手付金を差し引いた金額)を受領し、同時に司法書士による所有権移転登記の手続きを行います。
売主は事前にローンの残債がある金融機関と調整しておき、当日受け取った代金でローンを全額返済しなければなりません。
ローンが残っている場合、金融機関も決済に立ち会い、返済と同時に抵当権抹消の書類を司法書士へ渡します。
鍵の引き渡しや管理会社へのオーナー変更連絡、火災保険の解約手続きなどもこのタイミングで行います。
決済が完了すれば晴れて物件売却の完了です。最後に、仲介手数料の残額や司法書士への登記費用も支払います。
引き渡し後は買主に迷惑がかからないよう、速やかに入居者や関係各所へ所有者変更の連絡を済ませておきましょう。
売却後の確定申告
投資用マンションを売却した翌年の確定申告で、必要に応じて譲渡所得の申告を行います。
売却によって利益(譲渡所得)が出た場合は、長期・短期それぞれの税率に従って納税が必要です。
譲渡所得の計算では、売却価格から取得費(購入時の費用)や譲渡費用(仲介手数料など売却にかかった費用)を差し引いた額が課税対象となります。
損切りの場合、おそらく譲渡所得は発生せず赤字となるでしょう。
その場合、基本的には譲渡所得税は課税されません(確定申告自体も不要なケースがあります)。
ただし他の不動産を売却して利益が出た場合と損益通算できる可能性や、青色申告で不動産事業をしていた場合の損失繰越など、税務上検討の余地があるケースもあります。
自己判断が難しければ税理士や専門家に相談し、必要なら確定申告を行いましょう。
短期譲渡と長期譲渡で税率が2倍近く異なることも踏まえ、売却前に税金シミュレーションをしておくと安心です。
以上が売却の一連の流れです。不動産売却は人生で何度も経験するものではないため、分からないことも多いでしょう。
信頼できる不動産会社に仲介を依頼すれば、基本的には各ステップで適宜サポートしてくれます。不安な点は遠慮なく質問し、一つひとつクリアにしながら進めてください。
ワンルームマンション売却で損失をできるだけ抑える方法

損切り売却をする以上、少しでも実際の損失額を減らす工夫をしたいもの。
ここでは、売却時に損失を抑えるために取れる対策や考え方をいくつか紹介します。
適切な価格設定と販売戦略で高く売る
損切りとはいえ、少しでも高く売却できればその分損失は減ります。そのために、販売開始時の価格設定と戦略が重要です。
最初から強気の高値を付けすぎると売れ残り、結果的に値下げして損失が拡大する恐れがあります。かといって安く出しすぎる必要もありません。
査定を参考にしつつ、早期売却と売却価格のバランスをプロと相談して決めましょう。また、物件の見栄えを良くする努力も有効です。
空室の場合は室内をクリーニングし、簡単なリフォームや原状回復できれいに整えてから売り出すだけでも印象が違います。
古く汚れたクロスを張り替えたり、壊れた設備を修理したりすることで、買主に値引き材料を与えないようにしましょう。
数十万円のリフォームで買い手の印象が上がり、結果的にそれ以上の価格アップにつながることもあります。費用対効果を考えつつ、「やっておいた方が得な手直し」は済ませておくべきです。
入居中なら退去させずに売却する
前述の通り、賃借人がいる状態(オーナーチェンジ)で売却する方が高値が付きやすい傾向があります。
空室期間が長い物件だと「人気がない物件なのでは?」と勘繰られ、余計な不安を持たれることも。
もし現在入居者がいるなら、無理に解約させて更地(空室)にせず、そのままの状態で投資物件として売り出す方が得策です。
賃借人にはオーナー変更後も賃貸借契約が引き継がれることをきちんと説明し、協力を仰ぎましょう。
内見が難しい場合でも、入居中であること自体が価格維持にプラスになります。
逆に、空室の場合は早期に次の入居者付けを図ることも検討しましょう。
たとえ一時的に家賃を下げてでも新規入居者を確保できれば、「満室物件」として売却でき、結果的にトータルの損失が減る可能性があります。
複数の売却手段を検討する
一般的な仲介による売却以外にも、不動産業者への買取という選択肢があります。
業者買取は仲介手数料が不要で早期に確実に売却できるメリットがありますが、その分買い取り価格は相場より低めになる可能性が高いです。
時間に余裕があり損失圧縮を優先するなら、まずは仲介で一定期間売りに出し、それでも売れない場合に買取を検討すると良いでしょう。
また、最近は不動産一括査定サイトやAI査定サービスなども登場しています。これらを活用して複数社の見積もりや提案を比較することで、より有利な条件を引き出せるかもしれません。
いずれの場合も、「絶対に○月までに売り切りたい」など明確な事情がある場合は事前に担当者に伝え、戦略を練ってもらいましょう。
ローン残債への対策を準備
売却額がローン残高を下回るオーバーローン(債務超過)状態の場合、売却時に不足分を埋める資金計画が必要です。
自己資金で穴埋めできるなら問題ありませんが、難しい場合は金融機関に相談しましょう。
場合によっては、残債を無担保ローンに借り換える、保証人を立てて返済計画を立て直す等の対応が取れることもあります。
いきなり契約直前になって「残債を払えない」となると大問題ですので、査定額と残債を比較し、不足しそうなら早めに銀行に相談しておくことが大切です。
また、売却時には抵当権抹消の手続きも必要になるため、金融機関との調整は綿密に行いましょう。
税金面での優遇策を活用する
損失を少しでも減らすには、税負担を軽減する工夫も欠かせません。
まず、前述の長期譲渡所得の特例は大きな節税ポイント。購入から5年を超えて売却すれば譲渡税率が約20%に抑えられるので、もし利益が出る可能性がわずかでもあるならこのメリットを享受したいところです。
一方、売却損が出た場合、基本的にはその損失を他の所得(給与所得など)と相殺することはできません。
ただし、自宅を売却して損失が出た場合には一定の条件で他の所得と損益通算・繰越控除が可能な特例があります。
投資用でも将来マイホームに買い替える計画があるなら、その際に活用できる特例制度(居住用財産の買替え特例など)がないか調べてみましょう。
さらに、売却年に他の資産売却益がある場合は、同じ年内に損失物件を売却して譲渡益と譲渡損を相殺することで節税できます。
不動産に限らず株式等の譲渡益とも損益通算はできませんが、他の不動産やゴルフ会員権など一定の資産とは通算可能です。
複数の投資を行っている方は、タイミングを揃えて売却することも検討しましょう。税制は複雑なため、具体的な節税策は税理士に相談すると確実です。
減価償却などの経費計上を最大限活用
ワンルームマンション投資のメリットの一つに、減価償却費による節税効果があります。
建物部分の価値を耐用年数にわたり毎年経費計上する減価償却により、賃貸経営上は帳簿上の損失を出しやすく、それを給与所得等と損益通算して節税できる可能性があります(現在は高額減価償却による赤字の通算に制限があるケースもあります)。
これまで赤字経営でも「所得税・住民税が安くなっているからまあいいか」と続けてこられた方もいるでしょう。
しかし、毎月数万円規模の赤字だと節税効果を差し引いても現金流出が大きいため、単なる節税では追いつきません。
その一方で、これまでの運用期間中に減価償却による節税メリット自体は享受できているはずなので、累計の税金還付分を差し引いて実質的な損益を再評価してみることも大切です。
「思ったより税金が戻ってきていたのでトータルでは損失額が圧縮されていた」ということもあり得ます。
逆に、青色申告などで控除枠を使い切れていない場合は、売却前に経費を計上できるものは計上し切る、減価償却費を当期分まで漏れなく計上するといった対策で、最後の年の損益を調整しましょう。
例えば不要な家財の廃棄費用や、物件売却のための広告料などは譲渡費用や必要経費になり得ます。専門家と相談しつつ、使える節税策はしっかり使って手元資金の流出を最低限に抑える工夫をするといいかもしれません。
以上のように、損切り売却と一口に言っても、やり方次第で最終的に残る損失額は変わってきます。
ポイントは「情報を集め、比較し、交渉し、そして計算する」ことです。プロの知見も借りながら、できる準備と対策を講じて、有利な条件で売却を成功させましょう。
FGHの不動産売却サービスで安心のサポートを

ワンルームマンションの損切りにあたり、「専門家に相談しながら進めたい」「まずは自分の物件がいくらで売れそうか知りたい」という方も多いでしょう。
そんな方には、ぜひFGH株式会社の不動産売却サービスをご活用いただきたいと思います。FGHは収益不動産に特化した総合不動産グループで、ワンルームマンションなど投資用物件の売買仲介を数多く手がけているプロフェッショナル集団です。
FGHではお持ちの物件の現在の市場価値を無料で査定いたします。専門スタッフが物件の収益性や周辺相場を丁寧に分析し、適正価格の目安をご提示します。
査定結果をもとに、今売却すべきかもう少し運用すべきかといったアドバイスも受けられます。査定は匿名でも受け付けておりますので、いきなり個人情報を知られるのは不安…という方でも安心です。
特定の商品を無理に勧めるような強引な営業は行わないという基本方針を掲げており、安心してご相談いただけます。損切りすべきか迷っている段階でも、まずは専門家の意見を聞いてみることで気持ちが整理できるでしょう。
FGHは投資用不動産の売買に強みを持ち、豊富な買い手ネットワークを築いています。不動産投資家や法人顧客など、収益物件を探している多数の買主情報を有しているため、ワンルームマンションの売却でもスピーディかつ適正価格での成約が期待できます。
また、物件売却だけがゴールではありません。売却後の資金運用や税務手続きについても、FGHはしっかりサポートします。必要に応じて税理士やファイナンシャルプランナーと連携し、譲渡所得の申告や今後の資産運用プランニングまでお手伝いいたします。
また、売却運用セミナーといった独自のセミナーも定期開催しており、資産の組み換えや売却戦略について学べる機会を提供しています。再び不動産投資にチャレンジしたい方には、新たな投資物件の紹介や融資相談なども含めトータルで支援いたします。
ワンルームマンション投資の損切りは苦渋の決断かもしれませんが、適切に行えば将来の損失拡大を防ぎ、資産を守る賢明な一手となります。
本記事で述べたように、損切りの判断基準やタイミング、売却手順を理解し、できる限り損失を減らす工夫を凝らすことが大切です。
そして何より、今回の経験を次につなげる前向きな姿勢を忘れないでください。
勇気を持って一歩踏み出し、明るい資産形成のスタートを切りましょう。